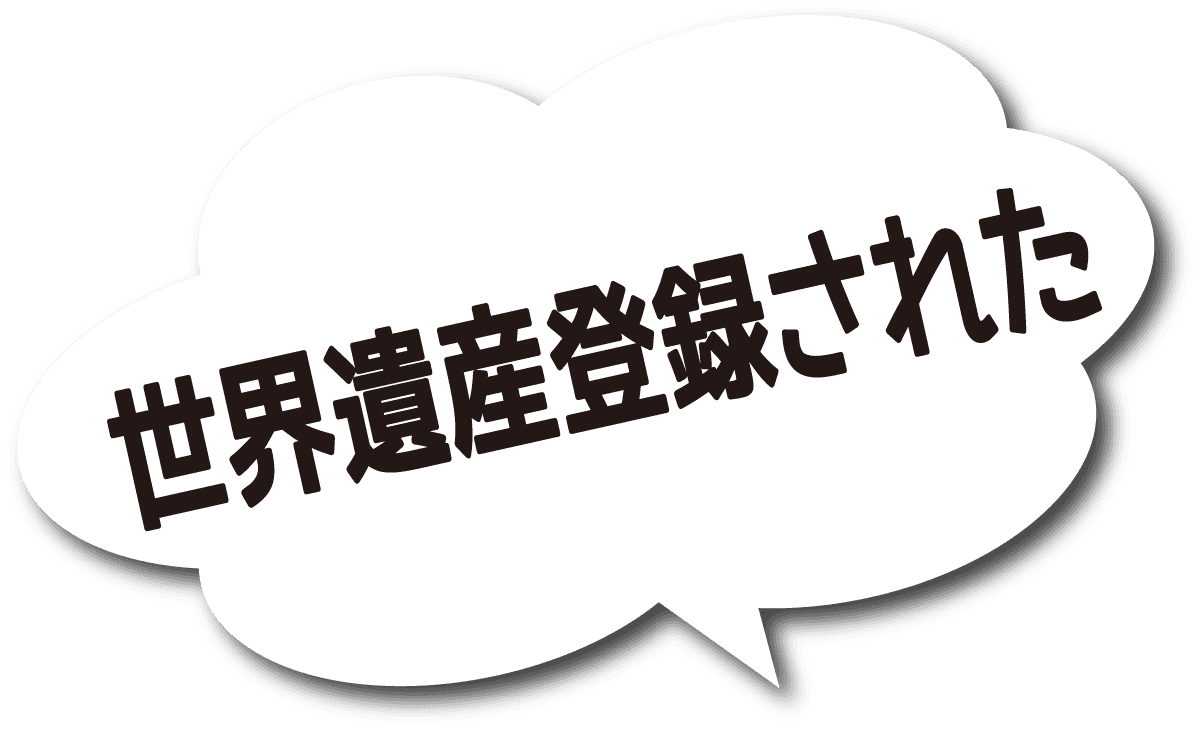

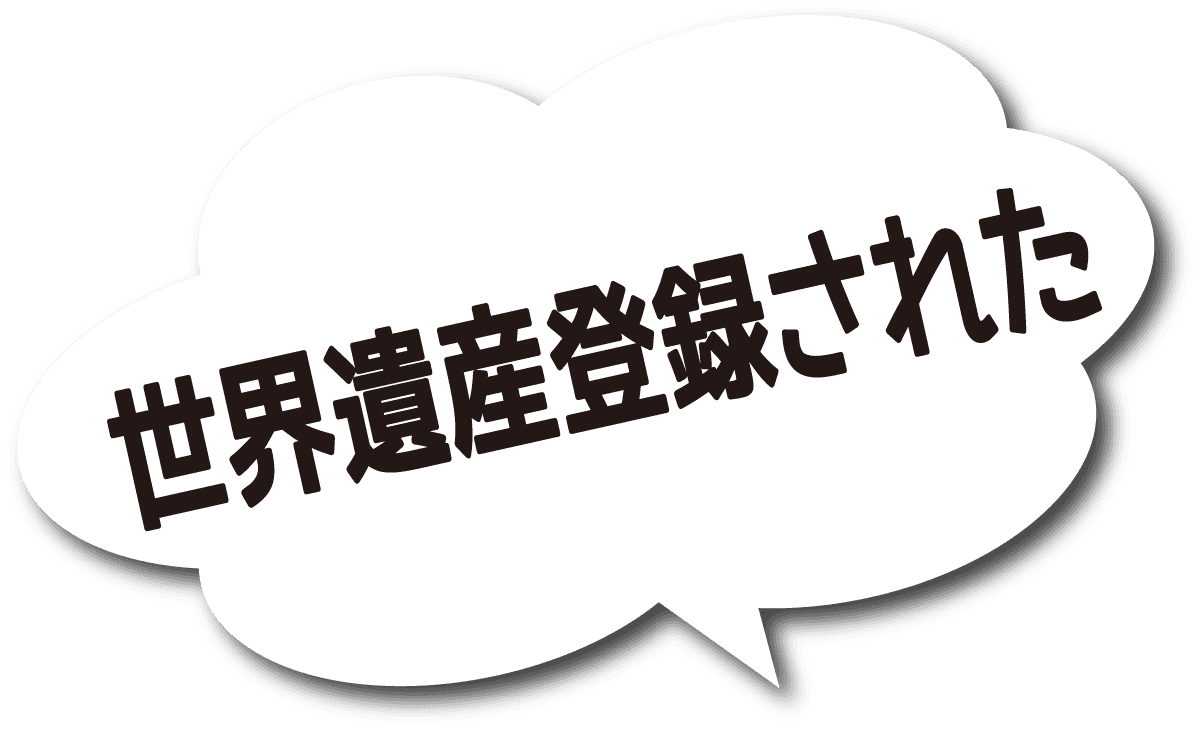


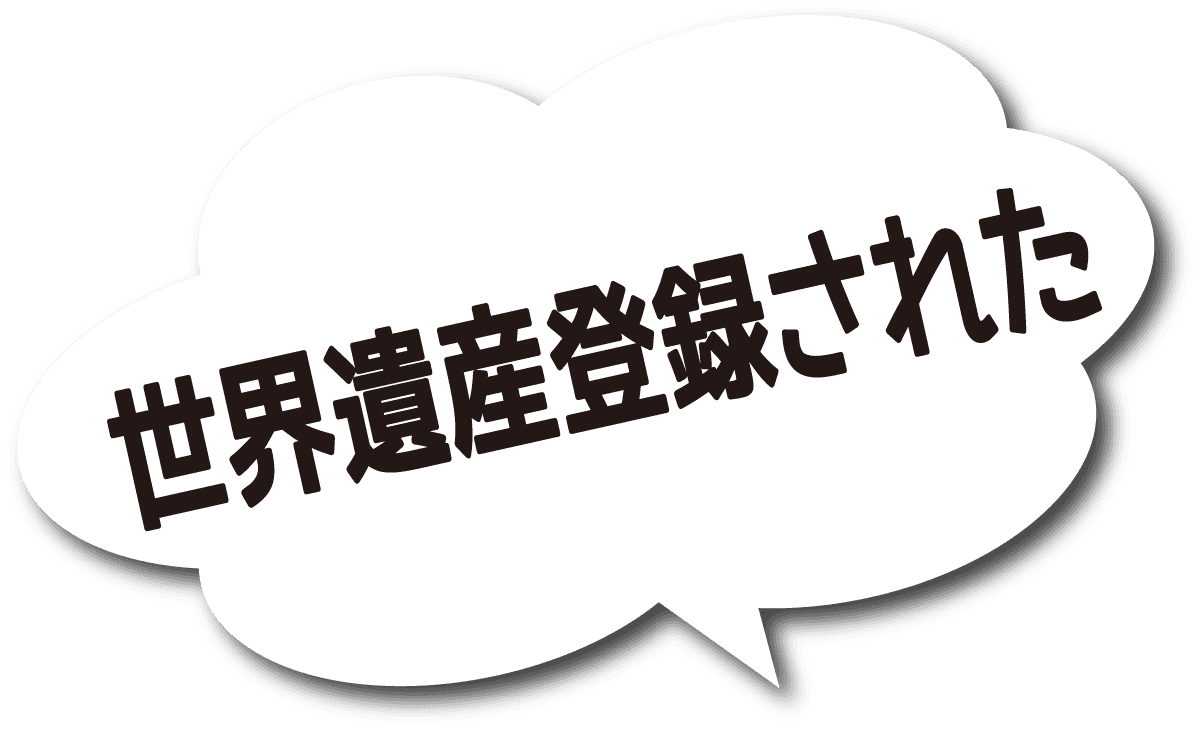

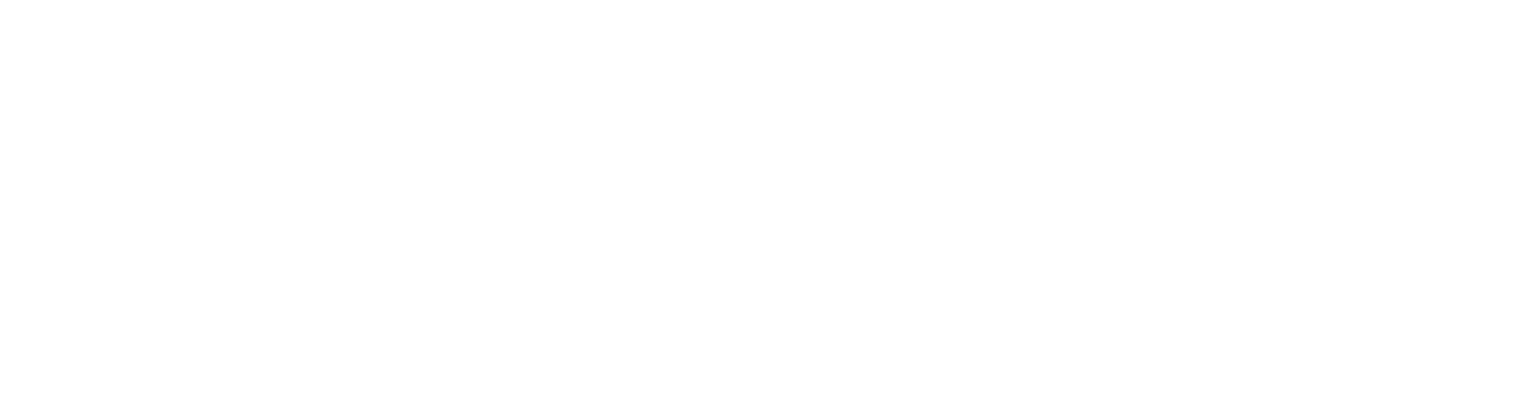
全国各地に点在している古墳には、様々な種類があります。有名な古墳として挙げられる前方後円墳だけでなく、それぞれに特徴や形が異なります。また古墳は古墳時代といわれる歴史があるほど、日本の歴史において色濃く残っているものでもあります。その古墳について、歴史的な目線から解説いたします。また古墳と関連の深いものとして知られている埴輪とは、どのような意味を持つものなのでしょうか。古墳と埴輪の関係性についてもご紹介しましょう。
株式会社つーる・ど・堺では、古墳をイメージさせる古墳クッキーを提供しています。古墳クッキーには様々なデザインが施されていますので、お土産にぜひチェックしてください。

古墳は一つの形ではなく、様々な種類や形が存在します。
前方後円墳は、円墳・方墳を組み合わせたような形をしている古墳です。鍵穴のような形をしており、世界遺産にも登録されている仁徳天皇陵古墳などが有名です。
円墳は、円形の古墳です。日本の古墳の中でも比較的多い形状の古墳であり、コンパクトなサイズ感が特徴です。
前方後円墳に似た帆立貝形は、前方部を前方後円墳よりもさらに短くした古墳です。古墳時代の中期に造られた古墳であり、王によって前方後円墳を作ることを禁止されたことでできた形ともいわれています。
方墳は四角形の古墳です。前方後円墳を使用することの多い王族も6世紀末以降から、この方墳を使用することが多くなったといわれています。

仁徳天皇陵古墳で知られる前方後円墳とは、どのような古墳なのでしょうか。この前方後円墳は、主に巨大な古墳に使用されている古墳です。鍵の形をしており、丸と三角を組み合わせたものとされています。前方後円墳の意味は、見た目のとおり前が方形で後が円形の形をしているという意味を持っています。そして、宇都宮市出身で江戸時代後期の儒学者である蒲生君平によって命名されています。
丸と三角を組み合わせた古墳は、女性を意味する丸と男性を意味する三角を表しており、卑弥呼とスサノオと呼ぶ方もいらっしゃいます。古墳には他にも様々な形がありますが、王族などの地位の高い方にはこの前方後円墳を使用しており、たくさんの埴輪などで囲んで埋葬します。
古墳はご存知のとおり、お墓としての役割があります。そして古墳は、王族や貴族などの地位を持った人々が埋葬されるお墓です。弥生時代に入ると、狩りや採取をメインとした暮らしから「生産経済」へと変貌を遂げます。生産経済になると身分に差が生じ、その地域をまとめる長が現れます。現に日本初の王女と呼ばれる卑弥呼も弥生時代に居たといわれています。王や長の立場を持つ人が現れるということは、そこで一つの組織が作り上げられ「クニ」が同時に出来上がることになります。またこの王や長が現れることで死後も王を祀るようになったことにより、自然と古墳などを造るようになったのではと推測されています。
埴輪は粘土を原料にして焼き上げられた土製品です。埴輪には「円筒埴輪」や「人物埴輪」をはじめとして、様々な形があります。埴輪は副葬品として古墳の中に入れたり、宗教的な儀式の際に使われています。また聖域を示すためや古墳の土が崩れないように置かれていたともいわれています。
埴輪は実際のところ、どのような目的を持って作られたのか具体的にわかっていないものでもあります。今後の発見により、目的がわかるようになるかもしれません。
堺市のお土産として人気の古墳クッキーは、古墳巡りの観光に最適なお土産の一つです。「もずふるサブレ」は堺市・羽曳野市・藤井寺市の3市をまたぐ百舌鳥古市古墳群をモチーフにしており、各市の古墳に関連する出土品や伝承をプリントしています。古墳クッキーのデザインは、ゆるかわいいほっこりするタッチの絵がプリントされています。古墳目当てに堺市や羽曳野市の周辺を訪れるなら、お土産に古墳クッキーはいかがでしょうか。
古墳には、前方後円墳をはじめ複数の種類があります。それぞれに形やサイズ感も異なり、広まる時期なども違うことが伺えます。また古墳は生産経済への移り変わりによって、王や長が立てられることがきっかけとなっている可能性があります。まだまだ未知な部分が多いことから、歴史ロマンを感じる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。また埴輪にもまだ解明されていない謎の部分も多く、今後の発見により新たにわかることが増えてくるでしょう。
堺で人気の古墳クッキー「もずふるサブレ」は、古墳好きの方にとってたまらないデザインが施されたお菓子です。堺土産にもなりますので、ぜひお手に取ってみてください。
| 商号 | 株式会社つーる・ど・堺 |
|---|---|
| 所在地 | 〒590-098 堺市堺区海山町1-8-4 |
| TEL | 072-227-4619 |
| FAX | 072-224-1466 |
| [email protected] | |
| WEB |